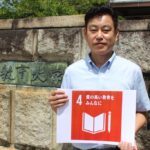2023年8月より、不登校の子どもたちのために特別な教育課程が編成可能な「学びの多様化学校」が、「不登校特例校」から名称を変更してスタートしました。
昨今、マスコミ等で、日本全国の学びの多様化学校の取り組みが取り上げられ、そこでの教育効果が周知されています。こうした学校で日々仕事をされておられる先生方や、学校に通う不登校の子どもたちやそのご家族にとっては、極めて重要な機会となっており、そこでの教育効果により、未来を拓かれる児童生徒にとってはかけがえのない場所であり、時間であると思います。
その上で、「学びの多様化学校」政策が抱える問題に対して、目を背けてはいけないのではないかという気持ちが一方で大きくなってきています。端的に言えば、「極めて少数の成功事例をもってして、日本全国の不登校問題があたかも解決に向けて大きく前進しているという錯覚を社会全体が抱いてしまい、声を出すことすらできない不登校で悩む本人と家族を置き去りにしてしまうことになってしまわないか。」という問題です。
そのように考える理由は、私の知る多くの「学びの多様化学校」で行われている取り組みが、ヒト(多数の専任教員の配置)、モノ(専用の設備構築)、カネ(それらを支えるための特別な予算)に支えられているために、大多数の学校に広まらない(広げることができない)仕組みとなっている点にあります。
各都道府県に数千人から万単位で在籍する不登校の児童生徒に対して、学びの多様化学校での数十人単位の受け入れ態勢では、今後も増加が予想される不登校児童生徒の問題を解決することにはつながらないように思います。
現在開催されている「中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会教育課程企画特別部会」では、不登校、日本語指導、特異な才能があるなど、個々の子供のニーズに焦点を当て柔軟な教育課程の編成に関する議論がなされるようですので、ぜひとも「学びの多様化学校」政策のブラッシュアップがなされ、日本全国の学校に広がる取り組みにつながってほしいと願っています。