今回は、文部科学省のデータからの分析ではなく、私の不登校問題に対する基本的な考えを述べておきたいと思います。
地震を例にするのは適切ではないのかもしれませんが、メタファーとしてのわかりやすさの観点から記したいと思います。地震に対する対応としては、地震が来るであろうことを予め知らせる「地震予知」、地震が来ることを予想しての「防災対策」、地震が来てしまった際の「減災対応」の3つがあるかと思います。
これを、現在の不登校対策に当てはめてみると、不登校の未然予防、不登校になる前段階の各種チェック、不登校になった子どもへの各種支援となるでしょうか。少し境界が曖昧なところもあるのですが、おそらく各教育委員会、学校では、これらを組み合わせながら対応されていると思います。とりわけ、最近では、初期段階の未然予防のところに力点が置かれている学校も少なくありません。
私の現時点での考えは、むしろ後期段階の、地震で言う減災対応や、不登校になった子どもへの各種支援に力点を置くことが望ましいのではないかということになります。
未然予防のところに力点が強く置かれた際に、次のような問題が生じるのではないかと思うからです。
1)未然予防に力点を置きすぎると、不登校に向かってしまった際に、子ども、保護者、教師の三者に、失敗してしまったという意識が強く生じ、より精神的にダメージを負う可能性があること
2)各種データの取得・分析によって、要因差・個人差の大きい未然予防に効果を発揮するかどうかが、現時点では保証されていないのではないかということ
もちろん、教育委員会や学校現場では、未然予防へのデータ蓄積と分析、そして対応が行われているかとは思うのですが、現実的には、ここ数年の不登校の実数値の増加が加速していることから、十分な効果にまでつながっていないとも読み取れます。
一方で、減災対応に力点を置く場合に気を付けなくてはならないのは、それが理念的理想論として強く語られすぎてしまうという危険性です。不登校になるのは特別ではない、なったとしても大丈夫、ゆっくりでいいからといった言葉は正しいといえます。その一方で、様々な形での社会的自立を最終的な目標とした場合に、そのことを保障・サポートすることのできる教育システムが不可欠です。むしろ、少し立ち止まっていても学び直しがきく、たとえ失敗したとしても再チャレンジできる社会の構造構築など、具体的な形でそれらを保障していかないと、言葉倒れではむしろ逆効果です。
そこで、不登校による学力面の減災対応を考えるにあたっての重要なキーワードは、ICTと生成AIであると思っています。ICTによるオンデマンド学習教材の充実は、いつでも、どこでも、どの段階からでも学習を支援することが可能になりますし、生成AIによるアバターやメタバースは、オーダーメイドに応じた個別対応を可能にします。それにより、子ども・保護者・教師が安心と落ち着きを取り戻すということが重要です。これらを、組織的、系統的、協働的に活用するという新たな教育文化の醸成が、不登校問題を解決する一つの糸口になると考えています。これからも、そうした具体的な教育システムの構築に向けて頑張っていきたいと思います。
投稿者プロフィール
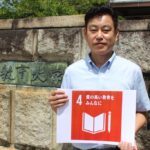
-
大阪教育大学卒業,大阪教育大学大学院修士課程修了,大阪大学大学院博士後期課程修了。博士(人間科学)。
大阪府内の公立小学校勤務8年の後,佛教大学専任講師,助教授,准教授,教授を経て,現在,京都教育大学教育学部教授。
京都教育大学では,小学校教員養成,中・高等学校(数学)教員養成に従事。近年の研究テーマは「生成AIを用いた算数・数学教育」。
小学校勤務時代,クラスで豚を飼うといった取り組みを3年間実践。フジテレビ「今夜は好奇心」にて1993年7月放映。第17回動物愛護映画コンクール「内閣総理大臣賞」受賞,第31回ギャラクシー賞テレビ部門「ギャラクシー奨励賞」受賞。2008年には『ブタがいた教室』として映画化。
コロナ禍の中で、日本語及び多言語に対応した算数・数学動画教材約3,300本を制作・公開した取り組みにより、2022年第7回IMS Japan賞優秀賞受賞、2023年第3回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞(教育の部)受賞、2023年日本民間放送連盟賞(特別表彰 青少年向け番組)最優秀賞受賞した。
著書に,「豚のPちゃんと32人の小学生」(ミネルヴァ書房),「脳科学の算数・数学教育への応用」(ミネルヴァ書房),編著に「初等算数科教育法序論」(共立出版),「オリガミクスで算数・数学教育」(共立出版)などがある。
最新の投稿
 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月28日:大阪市立柏里小学校での第2回公開授業に参加しました!
教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月28日:大阪市立柏里小学校での第2回公開授業に参加しました! 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月24日:文部科学省ホームページに黒田教育研究所が紹介されました!
教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月24日:文部科学省ホームページに黒田教育研究所が紹介されました! 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月25日:京都新聞に載せてもらいました!
教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月25日:京都新聞に載せてもらいました! 教育全般2025年11月11日【報告】2025年11月10日:兵庫県立夢野台高等学校で特別講義をしてきました!
教育全般2025年11月11日【報告】2025年11月10日:兵庫県立夢野台高等学校で特別講義をしてきました!

