今回が最後となります。実際に学校の最前線で働いておられる方々が不登校データを集約するのは、なかなか気持ち的にも難しい状況ではあると思うのですが、今回は不登校データの集約・分析方法に、都道府県ごとの偏りが、かなりみられるのではないかということの指摘です。
図は、私の方で小学生・中学生を合算して、1,000人当たり約何人の不登校児童生徒数、長期欠席児童生徒数になるのかを、都道府県別に示したものです。たとえば、北海道の場合、不登校児童生徒数は約42.2人、長期欠席児童生徒数は約57.9人(=42.2+15.7)となって、いずれも全国平均の約38.6人、約55.3人(=38.6+16.7)よりも高いことがわかります。
この観点からデータを見ると、例えば、中国地方の不登校児童生徒数は、岡山県で約29.6人と最も少なく、島根県で約48.8人と最も多くなっています。一方、長期欠席児童生徒数は、岡山県で約60.2人(=29.6+30.6)と最も多く、島根県で約54.5人(=48.8+5.7)と山口県に次いで低くなっています。メディアで取り上げられるのは一般的に不登校児童生徒数ですので、中国地方で大変なのは島根県となるのですが、学校に来ていない子どもの数値としては長期欠席児童生徒数になりますので、岡山県が実際には大変であるとなります。
こうした逆転現象は、四国地方でも生じており、不登校児童生徒数では高知県は全国平均以下で愛媛県は平均以上、長期欠席児童生徒数では高知県は全国平均以上で愛媛県は平均以下となっています。
私がここで述べたいことは、せっかく全国調査としてデータを集約・分析・公開しているのだから、都道府県が統一感を共有してデータを集約しないと、本当の実態がわからないのではないかということです。長期欠席児童生徒数には、不登校児童生徒数に加えて「病気欠席」、「その他」といった項目が入っていますが、この人数割合が都道府県において大きく異なっていることが、上記の逆転現象を起こすことにつながっています。
日本の長年の学校制度のあり方をも踏まえ、不登校の問題に対しては、何とか克服のための方策を打ち出していかなくてはならないと考えています。その際、上記の基礎データが重要であることは言うまでもありませんので、信頼性のあるデータとなるよう、皆で努力していく必要があると思います。

投稿者プロフィール
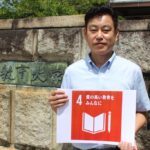
-
大阪教育大学卒業,大阪教育大学大学院修士課程修了,大阪大学大学院博士後期課程修了。博士(人間科学)。
大阪府内の公立小学校勤務8年の後,佛教大学専任講師,助教授,准教授,教授を経て,現在,京都教育大学教育学部教授。
京都教育大学では,小学校教員養成,中・高等学校(数学)教員養成に従事。近年の研究テーマは「生成AIを用いた算数・数学教育」。
小学校勤務時代,クラスで豚を飼うといった取り組みを3年間実践。フジテレビ「今夜は好奇心」にて1993年7月放映。第17回動物愛護映画コンクール「内閣総理大臣賞」受賞,第31回ギャラクシー賞テレビ部門「ギャラクシー奨励賞」受賞。2008年には『ブタがいた教室』として映画化。
コロナ禍の中で、日本語及び多言語に対応した算数・数学動画教材約3,300本を制作・公開した取り組みにより、2022年第7回IMS Japan賞優秀賞受賞、2023年第3回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞(教育の部)受賞、2023年日本民間放送連盟賞(特別表彰 青少年向け番組)最優秀賞受賞した。
著書に,「豚のPちゃんと32人の小学生」(ミネルヴァ書房),「脳科学の算数・数学教育への応用」(ミネルヴァ書房),編著に「初等算数科教育法序論」(共立出版),「オリガミクスで算数・数学教育」(共立出版)などがある。
最新の投稿
 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月28日:大阪市立柏里小学校での第2回公開授業に参加しました!
教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月28日:大阪市立柏里小学校での第2回公開授業に参加しました! 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月24日:文部科学省ホームページに黒田教育研究所が紹介されました!
教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月24日:文部科学省ホームページに黒田教育研究所が紹介されました! 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月25日:京都新聞に載せてもらいました!
教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月25日:京都新聞に載せてもらいました! 教育全般2025年11月11日【報告】2025年11月10日:兵庫県立夢野台高等学校で特別講義をしてきました!
教育全般2025年11月11日【報告】2025年11月10日:兵庫県立夢野台高等学校で特別講義をしてきました!

