ここでは、「学びの多様化学校」ならぬ「学びの機会保障学校」という考えを提案したいと思います。
近年の不登校の子どもたちの急増を踏まえると、学校制度そのものの見直しが必要であると感じますが、それはそれで大ごとですし、一朝一夕にはいかず中長期的視点から取り組まないといけませんのと、実施に伴う思わぬデメリットが生じる可能性もありますので、私も躊躇するところがあります。
一方で、「現在の学校制度の中でできることを」という短期的視点からであれば、少しは提案できることもあるかと思い、上記の「学びの機会保障学校」という考えを述べたいと思います。もちろんこの考えは「学びの多様化学校」の中でも提案されている内容にもつながりますが、「機会保障」ということを少し強調していきます。
「学びの機会保障学校」という考え方は、一人ひとりの不登校児童生徒にオーダーメイド的な学習支援を実施するという考えを一旦置いて、全ての児童生徒に学びの機会を保障するということに特化するというものです。具体的には、外発的であっても内発的動機付けであっても、学びたいという意欲が生じた不登校の児童生徒に対して、学びの機会と教材を無償で提供することのできるシステムを、各学校ないしは教育委員会レベルで構築・公開するというものです。
児童生徒一人ひとりの気持ちや状況に寄り添わない方法と捉えられるかもしれませんが、日本全国の学校に「普及」するためには、「何かを手放すことで、何かを残す」という、ある種の決断を行わなければなりません。私は、個々の子どもと保護者の精神的なサポートというところは学級の先生方の力に委ね、学力の維持・向上の点はICTを媒介とした外的資源を最大限に活用するという考えを取り入れるべきではないかと考えています。
ただし、この考え方による取り組みは、突拍子の無いものというわけではなく、かなり以前から実働してきたものでもあります。戦後間もない1952年には、都市部と地方との経済格差による教育格差を是正するために、当時、一般家庭に普及しつつあったラジオによる通信媒体を用いて、旺文社の大学受験ラジオ講座が開始されました。早朝・深夜の時間帯のラジオ番組として全国に配信されており、私も大阪府の能勢という田舎で生まれ育ちましたので、寺田文行先生の数学講座で大変お世話になりました。また、人種問題において就学前教育の充実を緊急課題としていたアメリカでは、一般家庭に普及しつつあったテレビによる通信媒体を用いて、1969年からテレビ番組「セサミ・ストリート」が開始され、就学全段階に必要とされる基本的な英単語と数字などを楽しみながら学べる工夫がなされました。さらには、2012年より、世界の大学がインターネットによる無料動画講座を公開するといったMOOC[Massive Open Online Course]が開始されました。高等教育を受けることのできない全世界の学びに渇望した若者(若者に限りませんが)たちをターゲットにしています。
いずれも双方向通信ではなく、単方向通信である点に特徴があり、単方向であることが、学びを必要とする広範な学習者への普及を可能にしました。「学びの多様化学校」が、こうした取り組みのハブ拠点(教材制作・配信/不登校の子どもの最新研究知見の提供)として機能し、一般の公立学校が「学びの機会保障学校」となり、有機的な連携関係を構築することができれば、短期的ではありますが、不登校の子どもたちの学習支援の一助となるのではないかと考えています。
投稿者プロフィール
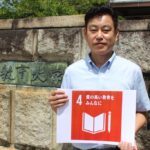
-
大阪教育大学卒業,大阪教育大学大学院修士課程修了,大阪大学大学院博士後期課程修了。博士(人間科学)。
大阪府内の公立小学校勤務8年の後,佛教大学専任講師,助教授,准教授,教授を経て,現在,京都教育大学教育学部教授。
京都教育大学では,小学校教員養成,中・高等学校(数学)教員養成に従事。近年の研究テーマは「生成AIを用いた算数・数学教育」。
小学校勤務時代,クラスで豚を飼うといった取り組みを3年間実践。フジテレビ「今夜は好奇心」にて1993年7月放映。第17回動物愛護映画コンクール「内閣総理大臣賞」受賞,第31回ギャラクシー賞テレビ部門「ギャラクシー奨励賞」受賞。2008年には『ブタがいた教室』として映画化。
コロナ禍の中で、日本語及び多言語に対応した算数・数学動画教材約3,300本を制作・公開した取り組みにより、2022年第7回IMS Japan賞優秀賞受賞、2023年第3回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞(教育の部)受賞、2023年日本民間放送連盟賞(特別表彰 青少年向け番組)最優秀賞受賞した。
著書に,「豚のPちゃんと32人の小学生」(ミネルヴァ書房),「脳科学の算数・数学教育への応用」(ミネルヴァ書房),編著に「初等算数科教育法序論」(共立出版),「オリガミクスで算数・数学教育」(共立出版)などがある。
最新の投稿
 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月28日:大阪市立柏里小学校での第2回公開授業に参加しました!
教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月28日:大阪市立柏里小学校での第2回公開授業に参加しました! 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月24日:文部科学省ホームページに黒田教育研究所が紹介されました!
教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月24日:文部科学省ホームページに黒田教育研究所が紹介されました! 教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月25日:京都新聞に載せてもらいました!
教育全般2025年12月1日【報告】2025年11月25日:京都新聞に載せてもらいました! 教育全般2025年11月11日【報告】2025年11月10日:兵庫県立夢野台高等学校で特別講義をしてきました!
教育全般2025年11月11日【報告】2025年11月10日:兵庫県立夢野台高等学校で特別講義をしてきました!

