次期学習指導要領改訂前夜となり、様々な新規教育用語が飛び交う時期となりました。
「自由進度学習」も近年、よく使われるようになった言葉の一つです。「自由進度学習」とは、教師がある一定のフレームを設定し、その中で、子どもが自ら学習計画を立て、自力で学習を進めたり、友達とディスカッションしながら学習を進めたりする学習スタイルを指すことが一般的です。また、自由進度学習的な取り組みを長年にわたって実施され、成果を上げている学校も紹介されたりしています。
この言葉の背景には、個別最適な学び、GIGAスクール構想といったものがあり、さらにはこれからの社会では、効率的な知識伝達型の一斉学習だけではなく、知識創発型を目指す新しい学習スタイルが必要との指摘も見られます。
一方で、日本の教育史の中で、自由進度学習的な取り組みがなされてきた時期もありましたが、深谷圭助先生のFBなどでは、それには相応の理由(異学年集団、進度が極端に異なる、教員不足など)があったことに言及されています。
また、中途半端な導入は、むしろ教員の過重負担や、学校全体としての教育効果といった点で、課題も少なくないとの指摘も見られます。
私は、この間、不登校の子どもたち、日本語指導が必要な外国人の子どもたち、そして、重度疾病のために院内学級や自宅療養している子どもたちの全国的な状況についてFBで発信してきました。そして、こうした子どもたちにこそ、「自由進度学習」の考えを活かして学習支援ができないかと考えています。ICTや生成AIの発展は、それを可能にする教育環境構築に大きく貢献するのではないかと期待しています。
改めて、「自由進度学習」は誰のために必要なのか?を考えていきたいと思います。
投稿者プロフィール
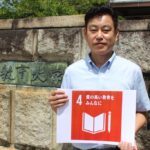
-
大阪教育大学卒業,大阪教育大学大学院修士課程修了,大阪大学大学院博士後期課程修了。博士(人間科学)。
大阪府内の公立小学校勤務8年の後,佛教大学専任講師,助教授,准教授,教授を経て,現在,京都教育大学教育学部教授。
京都教育大学では,小学校教員養成,中・高等学校(数学)教員養成に従事。近年の研究テーマは「生成AIを用いた算数・数学教育」。
小学校勤務時代,クラスで豚を飼うといった取り組みを3年間実践。フジテレビ「今夜は好奇心」にて1993年7月放映。第17回動物愛護映画コンクール「内閣総理大臣賞」受賞,第31回ギャラクシー賞テレビ部門「ギャラクシー奨励賞」受賞。2008年には『ブタがいた教室』として映画化。
コロナ禍の中で、日本語及び多言語に対応した算数・数学動画教材約3,300本を制作・公開した取り組みにより、2022年第7回IMS Japan賞優秀賞受賞、2023年第3回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞(教育の部)受賞、2023年日本民間放送連盟賞(特別表彰 青少年向け番組)最優秀賞受賞した。
著書に,「豚のPちゃんと32人の小学生」(ミネルヴァ書房),「脳科学の算数・数学教育への応用」(ミネルヴァ書房),編著に「初等算数科教育法序論」(共立出版),「オリガミクスで算数・数学教育」(共立出版)などがある。
最新の投稿
 教育全般2025年3月3日【告知】2025年2月16日:黒田恭史・葛城元編著『オリガミクスで算数・数学教育』の先行予約始まりました!
教育全般2025年3月3日【告知】2025年2月16日:黒田恭史・葛城元編著『オリガミクスで算数・数学教育』の先行予約始まりました! 教育全般2025年3月3日【議論⑤(了)】2025年2月5日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて!
教育全般2025年3月3日【議論⑤(了)】2025年2月5日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて! 教育全般2025年3月3日【議論④】2025年2月4日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて!
教育全般2025年3月3日【議論④】2025年2月4日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて! 教育全般2025年3月3日【議論③】2025年2月3日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて!
教育全般2025年3月3日【議論③】2025年2月3日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて!

