これまで「認知能力」と「非認知能力」という言葉の使い方は、二項対立的なイメージを持たせがちな用語であると感じてきました。教育の世界では、これまでも「形式陶冶か実質陶冶」や、「系統主義か生活(総合)主義」といった言葉が用いられてきましたが、どうしてもあれかこれか的な思考にひっぱられ、いずれかを批判的に捉えてしまう傾向に陥りがちだと思っていました。
なお、「社動スキル」という用語は、「社会情動的スキル」が長くて覚えにくいので、私がかってに省略して作った言葉ですが、「社動って何?」と聞かれた際に、社会において主体的に対応・適応する能力と、自己の感情(情動)を適切にコントロールする能力といった具合に、非常に答えやすい気がしています。
一方で、「非認知能力って何?」という質問に対しては、みなさん言うことが結構バラバラであったり、「言いよどまれる」場合が少なくないと感じています。 かなり勝手な発言ですので、お叱りを受けるかもしれませんが、「社動スキル」は、shadowのごろ合わせも少し意識していまして、少しでも広まってくれるといいなあと密かに願っています。
投稿者プロフィール
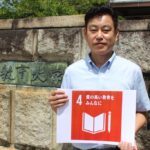
-
大阪教育大学卒業,大阪教育大学大学院修士課程修了,大阪大学大学院博士後期課程修了。博士(人間科学)。
大阪府内の公立小学校勤務8年の後,佛教大学専任講師,助教授,准教授,教授を経て,現在,京都教育大学教育学部教授。
京都教育大学では,小学校教員養成,中・高等学校(数学)教員養成に従事。近年の研究テーマは「生成AIを用いた算数・数学教育」。
小学校勤務時代,クラスで豚を飼うといった取り組みを3年間実践。フジテレビ「今夜は好奇心」にて1993年7月放映。第17回動物愛護映画コンクール「内閣総理大臣賞」受賞,第31回ギャラクシー賞テレビ部門「ギャラクシー奨励賞」受賞。2008年には『ブタがいた教室』として映画化。
コロナ禍の中で、日本語及び多言語に対応した算数・数学動画教材約3,300本を制作・公開した取り組みにより、2022年第7回IMS Japan賞優秀賞受賞、2023年第3回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞(教育の部)受賞、2023年日本民間放送連盟賞(特別表彰 青少年向け番組)最優秀賞受賞した。
著書に,「豚のPちゃんと32人の小学生」(ミネルヴァ書房),「脳科学の算数・数学教育への応用」(ミネルヴァ書房),編著に「初等算数科教育法序論」(共立出版),「オリガミクスで算数・数学教育」(共立出版)などがある。
最新の投稿
 教育全般2025年3月3日【告知】2025年2月16日:黒田恭史・葛城元編著『オリガミクスで算数・数学教育』の先行予約始まりました!
教育全般2025年3月3日【告知】2025年2月16日:黒田恭史・葛城元編著『オリガミクスで算数・数学教育』の先行予約始まりました! 教育全般2025年3月3日【議論⑤(了)】2025年2月5日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて!
教育全般2025年3月3日【議論⑤(了)】2025年2月5日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて! 教育全般2025年3月3日【議論④】2025年2月4日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて!
教育全般2025年3月3日【議論④】2025年2月4日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて! 教育全般2025年3月3日【議論③】2025年2月3日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて!
教育全般2025年3月3日【議論③】2025年2月3日:『無藤隆先生の隠居感想「1/2と1/3はどちらが大きいか?」という問題が私には分からない』に応えて!

